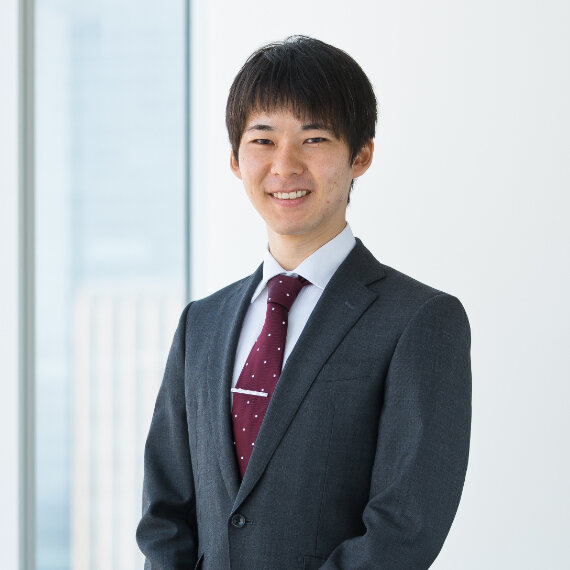ブログ
スタートアップ投資と会社法 -種類株主総会が投資実務に与える影響-
2025.06.03
はじめに
弁護士の彈塚寛之/藤森裕介です。
このシリーズでは、スタートアップ投資に関連する様々なトピックについて、日本の会社法との関係を分析することを試みています。内容については、執筆者の個人的見解であり、当事務所の見解ではありませんのでご留意ください。
本ブログでは、会社法上の種類株主総会に関する規定が、日本のスタートアップ投資の実務にどのような影響を与えているか、分析してみたいと思います。
種類株主総会とは
スタートアップによる特にシリーズA以降の資金調達においては、「A種優先株式」などの優先株式が発行されることが一般的です。この「優先株式」というのは、法律上の用語ではありません。会社法上は「種類株式」に該当し、普通株式よりも優先的な権利を有する種類株式のことを、俗に「優先株式」と呼びます。
そして、種類株式を発行する会社においては、特定の事項(株式発行、新株予約権の発行、株式分割・併合、組織再編行為等)を行う際に、ある種類株式の保有者に損害が生じる可能性がある場合、通常の株主総会とは別に、当該種類株主を構成員とする株主総会(種類株主総会)の決議を得る必要が生じます(会社法199条4項、238条4項、322条1項等)。
なお、定款で定めることにより、原則として種類株主総会決議を不要とする設計が可能ですが、株式の種類の追加や発行可能種類株式総数の増加についての定款変更は種類株主総会決議を排除できないため、例えば新シリーズの資金調達(新しい優先株式を発行する資金調達)を行う場合には、必ず種類株主総会決議が必要になります(会社法322条1項1号、2項、3項)。
定款に種類株主総会を排除する旨の定めを置く場合の注意点
上記のとおり、定款で定めることにより、一部の事項を除いて、原則として種類株主総会決議を不要とする設計が可能です(会社法322条2項)。
この際に、注意を要する点があります。例えば、シリーズAの資金調達においてA種優先株式を発行したスタートアップにおいて、A種優先株式が「種類株式」に該当することは当然ですが、この場合、元々発行されていた普通株式も「種類株式」に該当することになります。
そのため、原則として種類株主総会決議を不要としたい場合は、A種優先株式の種類株主総会のみならず、普通株式の種類株主総会も排除する必要があります。この点、定款において、A種優先株式の内容として「A種優先株式の保有者を構成員とする種類株主総会の決議を不要とする」という規定を置くだけだと、普通株式の種類株主総会を排除できません。全ての種類株式との関係で種類株主総会が不要になる文言になっているか、注意が必要です。この観点から、「当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株主総会の決議を要しない。」などとして、種類を特定することなく、全ての種類株式との関係で種類株主総会が不要となる旨を定めている例も少なくありません。
コンバーティブルエクイティとの関係
日本において、特にシード期のスタートアップが数千万円から数億円の規模で資金調達をする場合、優先株式ではなく、J-KISSに代表されるコンバーティブルエクイティ(CE)型の新株予約権が活用されることがあります。
CEの標準的な設計では、将来において一定金額以上の株式による資金調達(適格資金調達)が生じた場合に、CEは、その資金調達で発行される優先株式と同等の株式に転換されることになります。ただし、いわゆるディスカウントやキャップと呼ばれるコンセプトにより、適格資金調達に参加した新規投資家よりも1株当たりのバリュエーションが有利になる(同じ出資金額当たりで取得できる株式数が多くなる)ように、株式への転換計算が調整されることが通常です。
この調整を受けて、実際には、CEの保有者に対しては、適格資金調達において発行される優先株式そのものではなく、それとほぼ同一内容ではあるものの、1株当たりの金額が反映される部分(例えば、残余財産分配の優先分配額など)が微妙に異なる、亜種とも呼べる優先株式が発行されることになります。(例えば、CEの発行後にシリーズAの資金調達を迎え、新規投資家に対してA種優先株式が発行される場合、CEの保有者には、AA種やA2種などの別の優先株式が発行されることになります。)
そして、このようにCEの保有者に対して発行された亜種の優先株式は、会社法上は、独立の種類株式となります。
そのため、前述のとおり、例えば新シリーズの資金調達を行う場合には、この亜種の優先株式のみを構成員とする種類株主総会の決議が必要になり、実質的には、CEで出資した投資家に固有の拒否権を与えているのと同じ帰結になります。
(例えば、CEの発行後にシリーズAの資金調達を迎え、新規投資家に対してA種優先株式が、CEの保有者にはA2種優先株式が発行された場合、シリーズBの資金調達を行う際には、普通株主の種類株主総会、A種優先株主の種類株主総会に加えて、A2種優先株主の種類株主総会の決議が必要になります。)
CEは、本来的にはシード期に比較的少額の資金調達を行う際に、バリュエーションの算定や複雑な契約交渉をスキップして、簡易迅速にプロセスを進めるための手法です。
しかしながら、日本の投資実務においては、会社法上の種類株主総会制度により、CEにより出資した投資家にガバナンス上の強力な権利(種類株主総会を通じた一定の事項に対する拒否権)を認める帰結になりますので、留意が必要です。
なお、このような帰結を避ける実務的な工夫として、適格資金調達におけるCEの転換先を亜種にせず、CEの保有者がディスカウントやキャップのコンセプトにより得られたはずの差分を普通株式で付与するアレンジや、適格資金調達の際に締結する株主間契約において議決権拘束条項を規定し、CEにより出資した投資家が種類株主総会において独自の拒否権を発動できない仕組みを設けるアレンジなども提案されています。本ブログ執筆時点では一般的とは言い難い状況ですが、今後の実務の動向に注目する必要があります。
以上