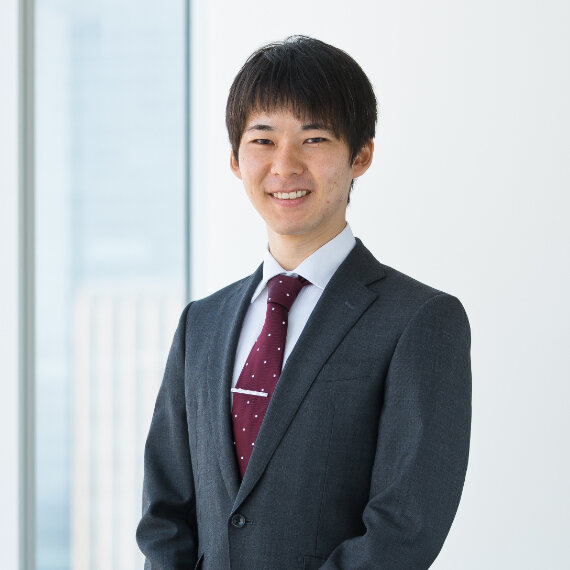ブログ
スタートアップ投資と会社法 -議決権の行使制限に関する定款規定-
2025.06.03
はじめに
弁護士の彈塚寛之/藤森裕介です。
このシリーズでは、スタートアップ投資に関連する様々なトピックについて、日本の会社法との関係を分析することを試みています。内容については、執筆者の個人的見解であり、当事務所の見解ではありませんのでご留意ください。
本ブログでは、スタートアップ投資に際して議決権制限に関する規定を設ける場合、会社法の観点からどのような留意点があるか、分析してみたいと思います。
議決権制限に関する規定
例えば、日本の銀行法上、銀行は、他の国内会社の議決権を子会社と合算して5%を超えて取得・保有することが原則として禁止されています。また、米国の銀行持株会社法(Bank Holding Company Act of 1956)上、銀行持株会社は、銀行以外の会社等の5%以上の議決権を保有することが原則として禁止されています。
このように、日本国内外の規制法により、一定の業種のエンティティについて、他の会社の議決権の保有比率に制限が生じることがあります。
そのようなエンティティがスタートアップに投資する際、規制法違反に当たらないようにする観点から、スタートアップの定款において、「投資家Aは、保有する議決権がx%を超える場合、超える部分の議決権を行使できない」という趣旨の規定を設けることが検討されるケースがあります。
この規定をスタートアップの定款に設ける場合、会社法との関係で、どのような論点が生じるでしょうか。
会社法上の論点(1)
まず、上記規定は、定款において特定の株主の権利に関する特例を設ける内容であるため、「株主ごとに異なる取扱いを行う」ものとして、会社法上、株式について「属人的な定め」(会社法109条2項)を規定したという整理になると思われます。
そして、属人的な定めを設けた場合、該当の株式は種類株式に準じて扱われるため(会社法109条3項)、当該投資家に対して固有の種類株式を発行したのと同じ取扱いになります。
ここで、種類株式を発行する会社においては、特定の事項(典型的には新シリーズの株式発行による資金調達等。会社法322条1項)を行う場合、通常の株主総会とは別に、株式の種類ごとに各種類株主を構成員とする株主総会(種類株主総会)の決議を得る必要が生じます。
※定款で定めることにより、一部の事項について種類株主総会決議を不要とする設計が可能ですが、株式の種類の追加や発行可能種類株式総数の増加等の定款変更については種類株主総会決議を排除できないため、新シリーズの資金調達等を行う場合には必ず種類株主総会決議が必要になります(会社法322条1項1号、2項、3項)。
そのため、上記規定を定款に設けると、将来スタートアップが資金調達をする場合等において、実質的には当該投資家の承諾が必要となる(当該投資家に種類株主総会を通じた拒否権を与える)可能性があると思われます。
会社法上の論点(2)
また、会社法上、株式に関する「属人的な定め」は非公開会社にしか認められないため(会社法109条2項)、上記規定を定款に設けた場合でも、上場する際には当該規定を廃止する必要があります。すなわち、上場に当たり、所定の定款変更や優先株式の普通株式への転換を行う際に、合わせてこの規定も廃止することになると思われます。
ここで、スタートアップ投資で活用される標準的な優先株式については、上場時にスタートアップ側が強制的に普通株式に転換する定め(取得条項)が設けられているため、仮に転換に非協力的な株主がいても、上場準備に支障が生じない建付けになっています。
他方、属人的な定めの廃止については、優先株式の転換と異なり、正面から定款変更の手続を行う必要があり、その際に当該投資家による種類株主総会決議が必要になる可能性があります(会社法322条1項1号ロ)。
そのため、当該投資家が定款変更に応じない場合、定款における属人的な定めを廃止することができず、結果として上場準備に支障が生じるリスクが否定できません。
おわりに
以上のとおり、特定の投資家との関係で議決権の行使制限に関する合意をし、これを定款上で定める場合、慎重に検討すべき法的な論点が複数存在します。
そのため、状況に応じて、定款で定める代わりに投資契約や株主間契約で同趣旨の規定を定めたり、定款で定める場合には上記論点から生じる懸念を低減するための工夫を合わせて検討するなど、柔軟な対応が必要になるものと思われます。
以上