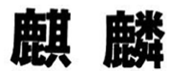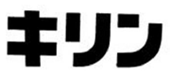ブログ
【裁判例】令和6年(行ケ)第10107号 キリンフーズ審決取消事件
2025.08.12
「キリンフーズ」と図形からなる商標を図形と文字を分離観察し、さらに文字を要部観察し、商標法4条1項11号に該当すると判断した知財高裁判決。
はじめに
結合商標の分離観察、要部観察の是非を巡る「キリンフーズ」審決取消訴訟(令和6年(行ケ)第10107号)の判決についてご紹介します。
「キリンフーズ」の文字と図形からなる本件商標が、「KIRIN」、「キリン」、「麒麟」等の文字からなる引用商標に類似し、商標法4条1項11号に該当するとして、無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例です。
原告は、大手ビールメーカー、大手清涼飲料水メーカーなどを傘下に持つ会社。被告は、本件商標の商標権者であり、長崎県で角煮まんじゅう、餃子の製造、販売を行う会社です。
特許庁は、本件商標に係る審査の段階では、本件商標の分離観察、要部観察を肯定し、引用商標との関係で商標法4条1項11号に該当すると判断して拒絶査定をしましたが、拒絶査定不服審判と無効審判では、いずれも「キリンフーズ」の文字の分離観察、要部観察を否定し、無効審判では、これに加えて、文字部分と図形部分の分離観察も否定し、引用商標とは非類似との判断を行いました。
|
本件商標 |
引用商標 |
|
指定商品 30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」
|
(29類,30類,32類ほか) キリン(標準文字) 麒麟(標準文字) きりん(標準文字) |
無効審判における特許庁の判断(記載は一部割愛しております)
「本件商標は、図形部分を顕著に表したものであり、その下段に相接するように、円輪郭の左右の幅に合わせて小さい文字で「キリンフーズ」の片仮名を配し、全体として同色をもって表され…、本件商標の全体構成において5分の4ほどを占める大きさで表されており、その大きさから本件商標において存在感を有するものといえる。
また、円輪郭内の動物図形は…下段の文字部分の「キリン」の意味の1つである…「麒麟」(想像上の動物)をモチーフにしたものという漠然とした印象を与え得るものであるが、図形部分からは特定の称呼及び観念を生じるとまではいえない。
また、本件商標の文字部分「キリンフーズ」の「キリン」の文字は、…図形部分より…「麒麟」(想像上の動物)をモチーフにしたものとの漠然とした印象を与えるものであるから、「キリン」の文字からも「麒麟」(想像上の動物)を連想させるものというのが自然である。
また、「フーズ」の文字は「食品」の意味を有するものであるとしても、「キリンフーズ」の文字部分は同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で一体的にまとまりよく表され、称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、かかる構成において「フーズ」の文字が特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいえないから、本件商標の文字部分は一体で把握される造語というのが相当である。
そうすると、本件商標の図形部分と文字部分は、「麒麟」(想像上の動物)の漠然とした印象を連想させるということで関連性があるものといえ、図形部分と文字部分が特に分離して看取されるといった必然性は見いだせず、両者はその構成どおり一体として看取されるものである。
そして、上記したとおり、本件商標は、特徴のある図形部分が顕著に表されていることから、その特徴ある図形部分が、取引者、需要者に強い印象を与えるものであり、その特徴のある図形マークの「キリンフーズ」として記憶にとどめるものということができる。
以上よりすれば、本件商標は、図形部分と文字部分は不可分一体のものと判断するのが相当であり、本件商標よりは、その文字に相応して「キリンフーズ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じない。」
特許庁は、本件商標の外観、称呼、観念について以上のように認定し、引用商標とは非類似と判断しました。
知財高裁の判断(記載は一部割愛しております)
これに対して、知財高裁は、本件商標の分離観察、要部観察を肯定し、本件商標が引用商標と類似するとの判断を行いました。
「本件商標は、図形部分と文字部分とからなる結合商標と理解されるところ、図形部分と文字部分とは、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、図形部分と文字部分とが一体として看取されるといった必然性も見出せないから、本件商標からは、文字部分を抽出し、当該文字部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そして、本件商標の指定商品は…食品であり、その需要者は一般消費者であると認められるところ、「フーズ」の語は上記のとおり食品を意味する英語である「foods」を片仮名表記したものとしてわが国において周知であること、企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社であることを示す例も…多数見受けられるところ、これらの例では著名な企業名が「フーズ」の前に冠されていること…からすると、本件商標の文字部分のうち「フーズ」の部分の自他識別力は、「キリン」の部分に比べ弱いものということができる。
本件商標の…図形部分は、その姿に加え、文字部分の一部である「キリン」と相まって、「麒麟」をモチーフにしたものという印象を与えるところ、図形部分及びそれを含む本件商標全体の態様や、前記のとおり、識別力の弱い「フーズ」の語が著名な企業名の後にくる例があること、及び「キリン」の文字部分に係る企業の周知性に鑑みると、本件商標の図形部分は、文字部分の「キリン」に看者の注意を集めるという面もあるということができ、図形部分が文字部分の「キリン」と共通する印象を与えることから直ちに、本件商標の図形部分と文字部分が不可分一体であって、商標の類否判断に当たって文字部分を要部として抽出することができない、とはいえない。
これらによると、本件商標は、文字部分のうちの自他識別力を有する部分である「キリン」を要部として抽出することができるというべきである。」
コメント
本件事案では、規範として「氷山印事件」(最高裁昭和39年(行ツ)第110号 昭和43年2月27日 民集22巻2号399頁)に加え、結合商標の類否に関わる「SEIKO EYE事件」(最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日 民集47巻7号5009頁)と「つつみのおひなっこや事件」(最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日 集民事228号561頁)が引用されておりますが、「リラ宝塚事件」判例(最高裁昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日 民集17巻12号1621頁)における判示事項を引用するとともに、その判旨に沿った判断がされたものといえます。
私見ではありますが、本件商標の無効審判の審理において、特許庁が、本件商標のような外観構成の商標の図形部分と文字部分の分離観察を否定し、一体不可分であるとの判断を行った点については、やや違和感があります。
一方、文字部分「キリンフーズ」の要部観察については、文字部分の外観構成の一体性が高い点や、「フーズ」が食品を意味する英語「Foods」を表す外来語として日本で広く知られているとしても、「ビール」「ハム」「チョコレート」のように直接的に食品名を示すものではないことも加味して、要部観察を否定していますが、こちらはあり得ない判断ではないように思われます。全般的な印象としては、特許庁の無効審判の審理においては、引用商標が、酒類などの飲料を中心とした周知、著名商標であって、そのなかでも「キリン」については防護標章登録もされているという事実をあまり考慮せず、本件商標と引用商標を非類似と認定たうえで、それを判断の根拠としたのではないかと推測します。
反対に、本件事案では、裁判所は、引用商標の周知、著名性、商品の関連性などを十分に考慮して、両商標間の混同のおそれを認定し、類似との判断を行ったものと推測され、これが特許庁と裁判所で全く異なる判断がなされることとなった理由の一つではないかと思います。
本件商標の商標権者は、同人の設立時の会社名が「キリン食品工業有限会社」であったのを、昭和60年に「キリンフーズ有限会社」に改名し、平成6年に「キリンフーズ株式会社」に組織変更しており、本件指定商品の「ぎょうざ」について、本件商標の図形部分と同じ図形部分を有し、その下側に小さく「KIRIN FOODS」の文字を配した本件商標と同じ称呼を生ずる商標を平成19年から使用していた事実を主張、立証していました。このことが間接的に、無効審判の結論に影響した可能性もあるように思います。
商標の類否判断、出所の混同の有無の判断においては、対象となる商標の周知、著名性の有無、それらの評価によって結論が変わってくることがあり、両当事者における商標の周知著名性の主張、立証を行うことの重要性をあらためて感じさせる事件でした。
Member
PROFILE